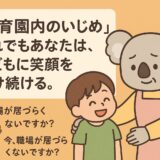ごめんなさいは必要なのか
「ごめんなさいは?」「こういう時どう言うの?」
保育の現場で、何度となく聞こえてくるこの言葉。
子ども同士のトラブルが起きたとき、大人がまず促すのは「謝ること」ではないでしょうか。
でも、ふと立ち止まって考えてみたくなったのです。
「ごめんなさい」を言わせること、本当に必要でしょうか?
言葉としての「ごめんなさい」
もちろん、「ごめんなさい」という言葉を知ることは大切です。
自分がしてしまったことで誰かが悲しんだとき、そこに「ごめんなさい」という言葉があることを知る。
それは社会の一員として生きていく上で大切な感情の表現です。
でも、「ごめんなさいって言えばいいんでしょ!」
「言ったのに許してくれない!」
そんな風に“言えば済むもの”として覚えてしまったら?
謝るよりも大切なこと
「ごめんなさい」が言えるようになった子が、
泣いている友だちに対して何も考えずに「ごめんね!ごめんね!」と繰り返す。
それが本当に、相手の気持ちに寄り添う姿でしょうか?
私は、むしろ「ごめんね」がない時間が大切だと思っています。
「…あ」
立ち止まって、考えてみる。
なんで泣いたんだろう。
何がいけなかったんだろう。
どうしたら、また一緒に遊べるのかな。
なんて声をかけたらいいのかな。
そんな風に、子どもが自分の頭で考え、心で感じることが大切なんです。
子どもの心の守り方
もちろん、友だちを泣かせてしまった事実に耐えられず、
「ぼく知らない!」と逃げてしまう子もいます。
それは、自分を守るために必要な反応です。
そんな時、怒らずに
「一緒に考えてみようか」
「どうしたらよかったと思う?」
と、そっと寄り添ってあげることが大人の役目です。
「許さない」も、学びのひとつ
そして、謝ったからと言って、相手が必ず「いいよ」と言ってくれるとは限りません。
「許さない!」
ときにはそんな強い言葉が返ってくることもあります。
でも、それもまた大事な感情表現。
「今は許せない気持ちなんだって」
と、その子の気持ちも丁寧に伝えてあげることで、
相手のことを考えるきっかけにもなります。
解決を急がなくていい
すぐに謝らせたり、すぐに許させたりしなくていい。
時間がかかってもいい。
でも、私たちはその経過を忘れずに見届けましょう。
子どもたちの心の変化は、とても小さくて、でも確かに進んでいくのです。
泣いてしまった子の心にも寄り添ってください。
「嫌だったんだね」「そうだよね」「許せないよね」
そう声をかけることで、「許さない」と言っていた子の心も、
少しずつ柔らかくなっていきます。
最後に
「ごめんなさい」を教えることは、ただの言葉の練習ではなく、
子どもたちが人と関わる力を育てる大切な過程です。
焦らず、諦めず、信じて待つ。
大人のその姿勢が、子どもたちの豊かな心を育てます。